「観葉植物の農家って本当に稼げるの?」
「大好きなグリーンで生計を立てたいけど、何から始めればいい?」
本記事は、そんなあなたの疑問やモヤモヤを解消するためにご用意しました。観葉植物ブームが続く今、農家として独立するチャンスは確かにあります。しかし、年収のリアルや始め方、将来性、求人状況までを一度に把握できる情報は意外と少ないもの。本記事では 観葉植物農家の年収相場 をデータと実例で紐解きながら、小さく始めて大きく育てるステップ、収益性を高めるコツ、さらに 求人の探し方 まで丁寧に解説していきます。
読み進めるうちに「自分でも一歩踏み出せそう!」と感じられる、具体的かつ実践的なヒントが満載です。観葉植物を愛するあなたが、将来の選択肢を広げられる内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。
- 【観葉植物の農家は儲からない?】観葉植物農家の現状や業務内容を紹介
- 【観賞植物で生計を立てることはできる?】観賞植物の農家の始め方とは?
- 観賞植物の農家の年収はどれくらい?
- 観葉植物農家の年収アップ(収益性)と将来性とは?【成功するポイントも考察】
- 成長が期待される観葉植物農家の未来とは?
- 観葉植物農家の求人状況とは?【仕事はある?】
- 【観葉植物と似ている仕事その①】多肉植物農家の年収と実態とは
- 【観葉植物と似ている仕事その②】花卉農家の年収と実態とは
- 【観葉植物と似ている仕事その③】ハーブ農家の年収と実態とは
- 【みんなが悩む疑問を解決します!】観葉植物の農家の年収や仕事内容に関するよくある質問5選
- 読者が今日から始められる!観葉植物農家を目指す第一歩とは?
- まとめ
- 🌿おまけトーク ~ホームセンターで“立ち止まる理由”ができました~
- 参考文献:
【観葉植物の農家は儲からない?】観葉植物農家の現状や業務内容を紹介
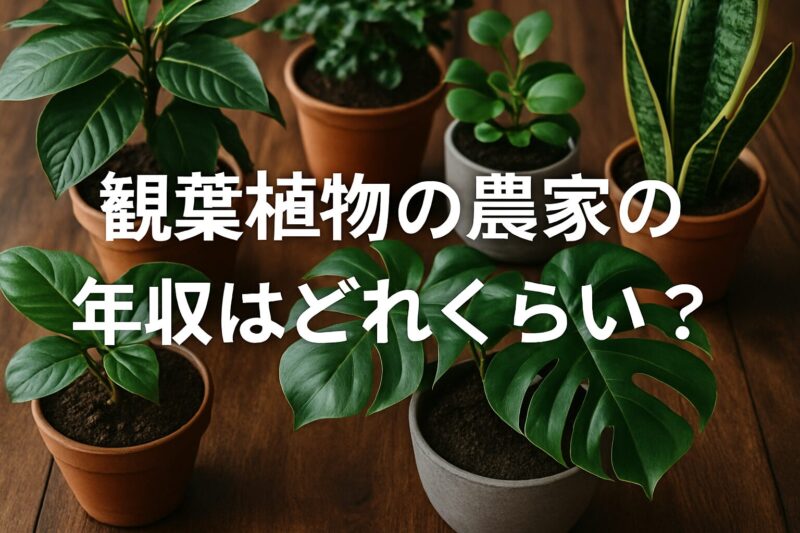
観葉植物農家は注目されているが、大きな課題も抱えるのが現状です。 観葉植物を専門に育てる農家は、都市部での需要拡大や室内緑化ブームを背景に、新たな農業分野として期待されています。特にコロナ禍以降、家庭やオフィスで観葉植物を飾る動きが強まり、市場自体は拡大傾向にあります。一方で、「観葉植物農家は儲からない」と言われることもあり、その裏には現在の業界が直面する課題が潜んでいます。
なぜ儲からないと言われるのか? 大きな理由の一つは収益構造の厳しさです。観葉植物は野菜のような生活必需品ではなく嗜好品の側面が強いため、景気や流行に需要が左右されやすく、市場価格が安定しにくい特徴があります。また、観葉植物の栽培には温室や照明など初期投資と維持コストがかかり、光熱費や燃料費の高騰は利益を圧迫します。特に温室栽培が中心の観葉植物農家では、高額な設備投資なしに高品質な植物を大量生産するのは難しく、小規模農家ほど利益が出にくい傾向があります。さらに繊細な植物ゆえに機械化が進みにくく人手が必要で、防虫防病の手間やコスト、人手不足なども収益を上げづらい要因です。
現場の実態エピソードを見てみましょう。例えば観葉植物農家のAさんは、最初「人気のモンステラを大量生産すれば儲かる!」と意気込んだものの、温室設備にかかる費用に驚き、さらに冬場の暖房代でほとんど利益が残らなかったそうです。失敗談として、「最初の年は手元に残ったのはモンステラではなく真っ赤な請求書だった」と苦笑していました(笑)。また、別の新人農家Bさんは、流行の品種に絞って育てたところ、次の年にはブームが去って在庫が売れ残り、大きな打撃を受けたとか…。このように、市場ニーズの読み違いやコスト計算の甘さで苦労するケースは決して珍しくありません。
それでも需要増加と工夫次第でチャンスはある。 観葉植物農家の仕事自体は、人々の暮らしに癒やしと彩りを提供できる魅力的な職業です。需要は近年安定または拡大しており、市場の変化に柔軟に対応できれば成長の可能性があります。実際の業務内容は、温室や露地で観葉植物を育成し、水やり・施肥・温度管理など日々の管理から、株分け・挿し木による増殖、生長した植物の出荷や販売まで多岐にわたります。華やかなグリーンに囲まれた仕事ですが、裏では泥だらけになって土をいじり、重い鉢を運ぶ体力仕事でもあります。「土いじりは好きだけど腰は痛い」なんて声も現場からは聞こえてきます(本音)。
友人も園芸店でアルバイトした際、夏の温室で熱中症寸前になり、「観葉植物のお世話って意外とハードだ…」と痛感した経験があるとのこと。。ですが、こうした現実を踏まえつつ、効率化や差別化で課題を克服できれば、観葉植物農家は決して夢のない仕事ではありません。
【観賞植物で生計を立てることはできる?】観賞植物の農家の始め方とは?

観葉植物農家は資格不要で始められますが、入念な準備と知識が成功のカギです。 観葉植物農家になるのに特別な資格は必須ではありません。農業一般に必要な農地や設備さえ整えば、誰でもスタートラインに立つことができます。ただし、だからといって無計画に始めるのは禁物。生計を立てるには栽培技術や経営ノウハウなど専門知識の習得が欠かせず、実際には準備段階から勉強と計画が必要です。
始める前に何をすべきか? まずは栽培の基礎を身につけることが重要です。観葉植物は種類によって最適な温度・湿度・日照条件が異なり、室内で健康に育てるには繊細な管理が求められます。大学の農学部や園芸専門学校で学ぶ道もありますが、必ずしも学歴は必要ありません。多くの人は園芸店や植物農家で修行したり、自治体やJAが主催する新規就農研修に参加したりして実践的に学んでいます。「百聞は一見に如かず」で、経験者の下で働いてみると土や葉の状態から植物の声を聞くコツが掴めるでしょう。また、ビジネス計画も忘れてはいけません。生産だけでなく販売まで視野に入れ、どの品目をどれだけ育て、どこに売るのかプランを練ります。小さく始めるなら自宅の庭やビニールハウス一棟から、規模を拡大するなら農地確保や資金調達(日本政策金融公庫の農業ローンや補助金活用など)も検討しましょう。
具体的なステップをいくつか挙げます。
たとえばステップ1:育てたい観葉植物を絞り込みます。「観葉植物」と一口に言っても、ポトスやサンスベリアのような定番から、希少な熱帯植物まで様々です。初心者なら育てやすく需要もあるポトスやパキラなどから始め、慣れてきたら希少種に挑戦すると良いでしょう。
ステップ2:小規模にテスト栽培。最初から大規模ハウスを建てるのはリスクが高いです。まずは副業・週末農家的に数十鉢ほど育ててみて、生育サイクルや販売の感触を掴んでみます。「趣味で育てていた観葉植物が増えすぎて、副業として販売開始→本格就農へ」というケースも実際あります。
ステップ3:販路開拓。育てた植物を販売してみましょう。地元のフリーマーケットやフリマアプリで売ってみると、思わぬ人気が出る品種が見つかるかもしれません。私の知人も趣味で増やしたモンステラをネットで売ったところ即完売し、「これはイケる!」と本格的に栽培規模を拡大した例があります。もちろん逆も然りで、売れ残りの山を抱えてしまうことも…(在庫管理は大切です💧)。
ステップ4:本格始動。反応が良かった品種や販売方法に絞って、生産量を増やします。必要に応じて農地を借りたり温室設備を導入したりして、事業計画を推敲しながら晴れて専業農家として歩み始めましょう。
小さく始めて大きく育てる心構えで! 観葉植物農家への道は、いきなり大農園のオーナーになるというより、「苗を育てるように徐々にステップアップ」していくイメージです。初めは副業や小規模からでも問題ありません。むしろ小さく始めて試行錯誤することで、致命的な失敗を避けられます。幸い、観葉植物は狭いスペースでも育てられるものが多いので、都市部の自宅ガレージからスタートすることも可能です。実際、海外ではガレージで観葉植物を育てネット販売し、副業で年収6桁ドル(1000万円超)を稼ぐ例も報告されています。もちろん誰もがそううまくいくわけではありませんが、工夫次第でチャンスが広がる業界と言えるでしょう。大切なのは、情熱と計画性を持って継続することです。「植物とともに自分も成長する」つもりで、一歩ずつ進んでいきましょう。
観賞植物の農家の年収はどれくらい?

観葉植物農家の年収は経営規模や販売方法によって大きく異なります。 一般に個人経営の小規模農家の場合、年収は300万~600万円程度が一つの目安と言われます。一方、大規模に展開する法人経営の農園などでは1,000万円以上の収益を上げるケースもあります。つまりピンからキリまで幅広いというのが正直なところです。平均的には観葉植物も含む花き農家全体で年収300万~500万円前後ともされ、サラリーマンの平均年収と比べるとやや低めかもしれません。しかし、これはあくまで平均値。市場ニーズを捉えて成功している農家の中には、年収1,000万円超を実現している例も確かに存在します。反対に、新規就農して間もない小規模農家では年収100万~200万円程度にとどまることもあり、収入格差が大きい業界とも言えます。
なぜこんなに差が出るのか? ポイントは経営規模と付加価値です。大規模農家は温室などの設備投資を行い、一年を通じて安定供給できる体制を整えているため、出荷量も多く収益チャンスが多い傾向があります。また高価格で取引される希少種や人気種を大量生産できれば、その分売上も伸びます。
一方、小規模農家は出荷量に限りがあるため売上規模が小さくなりがちです。さらに販路の違いも収入に直結します。卸売市場に出すだけでなく、直販やネット通販など中間マージンを省く売り方をしているかどうかで手取りも変わります。たとえば、自分でECサイトやSNSを活用して販売すると、利益率を高められる可能性があります。また、最近ではサブスクリプションサービス(定期便)で観葉植物を届けるビジネスモデルも注目されています。逆に言えば、伝統的な卸任せの販売だけだと価格競争に巻き込まれやすく、年収も伸び悩むかもしれません。
成功しているケースとそうでないケースを比較しましょう。ある成功事例では、観葉植物農家Cさんはインテリアショップと提携しておしゃれな大型観葉植物をレンタル・販売するサービスを展開し、大口契約を獲得して年商を大きく伸ばしました。彼の農園の規模自体はそれほど大きくありませんでしたが、付加価値の高いサービスを組み合わせることで高収入を実現しています。また、ネットショップで直販することで中間業者を挟まず利益率を向上させたそうです。
一方、苦戦しているケースでは、Dさんは家族経営で観葉植物を育てていますが、地元の花卉市場への卸売がメインのため単価がどうしても低く抑えられてしまいます。加えて、生産した植物の一部は市場の需要と合わず廃棄せざるを得ないことも…。その結果、ここ数年の年収は200~250万円程度で伸び悩んでいるそうです。「規模拡大か販路拡大か、どちらかを模索しないと正直しんどい」とDさんは話してくれました。こうした例から、どのように収益を上げる工夫をしているかが年収の明暗を分けると言えます。
観葉植物農家の年収は自分次第で変えられる余地があります。 平均を見ると決して「楽に高収入」とはいきませんが、経営の工夫次第で大きく収入を増やすことも可能です。特に最近は観葉植物ブームで市場が活気づいており、ニーズにマッチしたビジネスモデルを構築できれば十分生計を立てられます。実際、農林水産省の統計によれば花卉栽培農家の平均年収は約314万円ですが、これはあくまで統計上の数字。自分の努力で500万円、700万円と収入を伸ばしている人もいますし、独自ブランドを確立して「観葉植物長者」と呼ばれるような存在になることも夢ではありません。重要なのは、自分の農園の規模や強みに合った戦略で収益を上げること。次の章では、その年収アップの秘訣や将来性について掘り下げていきましょう。
観葉植物農家の年収アップ(収益性)と将来性とは?【成功するポイントも考察】
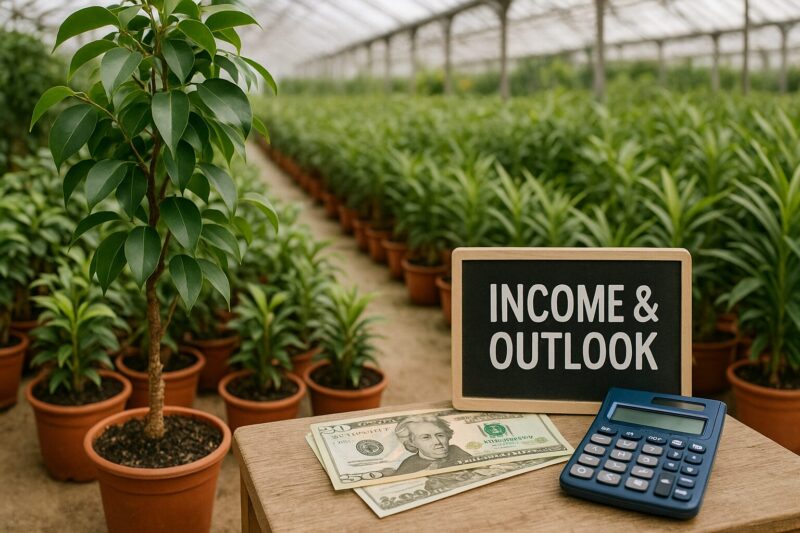
観葉植物農家が収益を上げ成功するためには、「売り方」「育て方」「差別化」の3つがポイントです。
年収アップには単にたくさん育てるだけでは不十分。需要の高い品種を選ぶこと、効果的な販売チャネルを持つこと、そして経営コストを抑える工夫が欠かせません。さらに、観葉植物市場はトレンドの移り変わりがあるため、常に新しい品種や販売方法を模索する姿勢も将来の成長に繋がります。
成功する観葉植物農家の共通点とは? いくつか重要なポイントに分けて考えてみましょう。
- ①儲かる品種・付加価値商品の育成: 利益を伸ばすには単価の高い植物を扱うことが近道です。具体的には、ギフト需要のある観葉植物の大型鉢や、珍しい希少品種(例:斑入りモンステラやレアなフィカス属)などは高値で取引される傾向があります。近年、斑入りのモンステラがネットオークションで数十万円になるケースも話題になりました。もちろん高単価品は栽培に手間も技術も要しますが、その分リターンも大きいです。また、単体で売るだけでなく付加価値商品を作るのも方法です。おしゃれな鉢カバーとのセット販売や、インテリアコーディネート込みの販売、植物レンタルやリース事業など、「植物+α」のサービスはお客様も喜び、収益性も上がります。観葉植物や花卉はSNS映えする商材なので、観光農園やフォトスポットとして開放するのも付加価値戦略の一つです。
- ②販路とマーケティングの工夫: 良い商品も売れなければ収入になりません。販売チャネルの多様化は年収アップの鍵です。従来の卸売市場に加えて、直売所を設けたりネットショップを開いたりすることで、中間マージンを省いて利益率を高めることができます。特に現代はインターネットのおかげで、小規模農家でも全国のお客様に直接販売できます。実際、SNSを上手に活用してファンを増やしている農家も多いです。InstagramやTwitterで育成過程を発信し、ファンから直接注文を受けたり、ブログやYouTubeで育て方を紹介して信用を得たりといった取り組みは、地味なようで大きな効果があります。「フォロワー1万人=見込み顧客1万人」とも言えますよね。私も趣味で観葉植物の写真をInstagramに投稿していますが、コメントで「この植物売ってほしい!」と言われたこともあり、SNSの力を実感しました(残念ながらそのときは売り物がなくお譲りできませんでしたが…苦笑)。さらに、観葉植物の定期便サービスなど時代に合った販売モデルを検討するのも良いでしょう。最近では、決まったサイクルで季節の観葉植物が届くサブスクサービスも登場しており、安定収入を確保する新しい手法として注目されています。
- ③コスト管理と技術向上: 「収入を増やす=支出を減らす」も重要な視点です。観葉植物農家の場合、光熱費や苗の仕入れ費用が大きなコストです。そこで、省エネ型の設備に更新したり、自家栽培で苗を増やして種苗費を削減したりといった工夫が欠かせません。自治体や国の補助金を活用して太陽光発電を導入し電気代を抑えた農家もいます。また、最新技術の活用も見逃せません。例えば組織培養(ティッシュカルチャー)という技術を使えば、小さな組織片から短期間で何百株ものクローン苗を増やすことも可能です。従来の挿し木や種まきより格段に増殖効率が高く、病害虫フリーの苗を大量生産できるため、将来的に収益を大きく伸ばせる潜在力があります。実際、観葉植物業界でもランやシダ類などで組織培養が取り入れられており、生産スピードと品質向上に寄与しています。技術力を高めることで高品質な植物を安定生産できれば、ブランド化も夢ではありません。あるベテラン農家は「技術は裏切らない。腕を磨けば価格競争に巻き込まれにくくなる」と語っていましたが、その言葉通り、高い技術に裏打ちされた植物は市場で一目置かれ、多少高くても売れていく傾向があります。
成功のポイントを押さえた農家Eさんのケース。 Eさんは観葉植物農家歴10年。彼は希少性の高いアグラオネマという観葉植物に注目し、自ら品種改良した美しい葉色の新品種を開発しました。そしてそれを「一点もののコレクター向け観葉植物」としてブランド化し、ネット限定で販売。希少価値と独自ブランド戦略により、一株数万円という高価格にも関わらず予約が殺到しました。また、EさんはYouTubeで育て方講座**を開きファンを増やしつつ、有料会員向けに苗を優先販売する仕組みを作りました。その結果、彼の年収はここ数年で大幅にアップし、1,000万円に迫る勢いとのことです。「正直、最初の2~3年は年収200万円台でアルバイトもしながらでした。でもコツコツやってきたことが花開いてきました」と笑顔で語るEさんの姿はとても印象的でした。逆に、課題が残るケースとしては、観葉植物農家歴2年のFさん。Fさんは珍しい品種にばかり手を広げすぎて管理が追いつかず、多くの株をダメにしてしまいました。また販売も知人任せでマーケティングが弱く、せっかく育てた植物をさばき切れない状況です。このままでは収益は上がらず苦しいため、現在は品種と経費を絞り込んで立て直しを図っているそうです。このように、成功には戦略と努力が不可欠であり、偶然や運だけに頼ることはできません。
観葉植物農家の将来性は明るく、成功のカギはトレンド適応と独自性にあります。 観葉植物ブームは一過性ではなく、人々のライフスタイルに根付いたものになりつつあります。特に在宅ワークの普及で自宅にグリーンを求める人が増え、市場規模は今後も堅調に推移する見込みです。また、IT技術や物流網の発達で、小さな農家でも全国相手に商売できる環境が整っています。観葉植物農家として成功するには、この追い風を捉えつつ、常に新しい価値を提供し続けること。「うちから買いたい!」と思ってもらえるような魅力づくりと信頼構築が、収益アップと将来の発展に直結するでしょう。
成長が期待される観葉植物農家の未来とは?

観葉植物農家の未来は、需要拡大と技術革新によりさらなる成長が期待できます。
今や観葉植物はただのインテリアを越えて、SDGsやウェルビーイング(心身の健康)にも関連した存在です。室内に植物を置くことでリラックス効果や空気浄化効果が得られることは科学的にも知られており、企業オフィスや公共施設でも室内緑化のニーズが高まっています。こうした流れは観葉植物農家にとって追い風であり、将来的にも安定した需要が見込めるでしょう。
未来を明るくする要因と課題を整理してみます。まず、若い世代の植物ブームがあります。SNSにはおしゃれな植物の写真が溢れ、「植物のある暮らし」が一つのトレンドになっています。特に20~30代の若い層が熱帯植物やサボテンなどに興味を持ち、コレクションする動きも見られます。この新規ファン層の増加は市場の拡大要因です。一方で心配されるのは、ブームが去ったときに需要が落ち込まないかという点。しかし観葉植物の場合、一度環境に取り入れると世話を続ける必要があるため、ブーム後も買い替え需要や増殖ニーズが一定数発生します。さらに、コロナ禍で一時的に急伸した需要は最近落ち着きを見せつつありますが、それでもパンデミック前より高い水準で推移しているとの調査もあります。つまり、爆発的成長は落ち着いても底堅い市場になったと考えられます。
技術面では、前述の組織培養技術やIoTを活用したスマート農業の導入で、生産効率が飛躍的に向上する可能性があります。例えば、環境制御システムで温度・湿度・日照を自動管理し、AIが植物の成長をモニタリングして最適な潅水タイミングを指示する、といった次世代農業がすでに一部で始まっています。また、品種改良の進展も期待されます。より美しい葉模様や耐陰性・耐乾性に優れた新品種が開発されれば、市場をさらに活性化できるでしょう。
海外の動向も参考になります。世界的に見ても室内園芸市場は拡大を続けており、アメリカの独立系ガーデンセンターの調査では「依然として観葉植物の需要・売上は増加傾向にある」という報告があります。ただ、パンデミック期ほどの急成長ではなくなり安定成長期に入ったとの見方もあります。これは裏を返せば、過熱なブームによる乱高下が落ち着き、計画的な経営がしやすくなるということでもあります。また海外では、観葉植物をサブスクリプション形式で届けたり、プラントレンタル(緑のレンタルサービス)がビジネスとして定着しつつあります。日本でもオフィス向け植物レンタル業は以前からありますが、個人宅向けの定期レンタルなど新たな市場開拓の余地がありそうです。
総じて、観葉植物農家は「緑を届けるプロフェッショナル」として今後も社会に求められ続けるでしょう。
人々が植物に求める価値は癒しや潤いといった精神的なものから、インテリア性、さらには環境貢献までますます広がっています。そのニーズに応えられる観葉植物農家は、単に植物を生産販売するだけでなく、暮らしを豊かにするパートナーとして期待される存在です。もちろん、気候変動に伴う生産環境の変化や輸入植物との競合など、乗り越えるべき課題もあります。しかしそれらを克服する技術と知恵を備えた農家が生き残り、未来の観葉植物業界をリードしていくでしょう。「枯れないビジネスモデル」を育て上げ、観葉植物農家として輝く未来を目指しましょう。
観葉植物農家の求人状況とは?【仕事はある?】

観葉植物農家の求人は決して多くはないものの、探せば存在し、未経験者歓迎のケースもあります。 一般的な農業求人に比べればニッチですが、観葉植物の生産農場や園芸会社が人材を募集することがあります。特に花卉園芸全般で見ると求人は一定数あり、「花や観葉植物が好きな人歓迎」「未経験OK」「正社員登用あり」といった条件の募集も見られます。つまり、観葉植物農家への就職の道はゼロではないのです。
観葉植物や花の栽培に関する求人を見つけるには、農業専門の求人サイトを活用するのが近道です。たとえば農業ジョブやみんなで農家さんといったサイトでは、全国の花卉農家・植物農園の求人情報が掲載されています。そこには観葉植物を扱う農園のアルバイト募集や正社員募集も含まれています。また、地元のハローワークやJA(農協)のウェブサイトでも、地域の園芸農家の求人が出ていることがあります。都市近郊では、「植物工場スタッフ募集」「グリーンレンタル会社のメンテナンス担当募集」など観葉植物関連の仕事が見つかることもあります。
求人形態としては、正社員よりアルバイトや期間契約が多いかもしれません。観葉植物は繁忙期と閑散期があるため、繁忙期だけ短期アルバイトを採用する農家もいます。しかし、熱意を持って働けば正社員登用や独立のチャンスもあります。実際、短期バイトからスタートして経験を積み、独立して自分のハウスを構えたという人もいます。求人要件は「要普免(配送などで)」「体力に自信のある方」程度で、特別な資格や経験不問のことが多いです。園芸未経験でも「植物が好き」「やる気がある」ことをアピールすれば採用される可能性は十分あります。
【求人情報の一例と応募のコツ】 例えばある求人サイトには、「【未経験歓迎】観葉植物の生産スタッフ募集(正社員)勤務地:千葉県 月給18万円~」という募集が出ていました。仕事内容は温室内での植え替え・水やり・出荷作業などで、植物好きな若手が活躍中とのこと。また別の会社では、「商業施設向け観葉植物メンテナンススタッフ(契約社員)要普免、園芸知識不問、研修あり」という求人も。応募する際は、「なぜこの仕事をやりたいのか」**熱意を伝えるのが大切です。植物が好きになったきっかけや、自分が育てた経験談などを交えると良いでしょう。面接ではきっと「きつい作業もありますが大丈夫ですか?」と聞かれるので、笑顔で「泥んこ作業も覚悟の上です!」と答えられると◎です。なお、SNSやコミュニティでの情報収集も侮れません。Instagramで観葉植物農家のアカウントをフォローしておくと、「実はスタッフ募集中です」なんて投稿があったりします。私自身、Twitter経由で「知人の農家がスタッフ探してる」と情報をもらったことがあります。業界の横の繋がりは狭いので、ネットワークを作っておくと思わぬチャンスが舞い込むかもしれません。
観葉植物農家の求人は少数精鋭ですが、“好き”を仕事にできる貴重なチャンスです。
花や野菜の農家に比べ募集は絞られますが、逆に言えば競争率もそれほど高くないとも言えます。もし求人を見つけたら思い切って飛び込んでみるのも一つの手です。そして経験を積めば、将来独立して自分の農園を始めることも夢ではありません。未経験からスタートしたスタッフが何年後かに自分の観葉植物ショップを開いた、なんて話もあります。まずはチャンスを逃さず掴むこと。観葉植物への情熱と勤勉さがあれば、きっとあなたを必要としてくれる職場が見つかるでしょう。仕事探しも植物のお世話と同じで、「根気」が大事ですよ!
【観葉植物と似ている仕事その①】多肉植物農家の年収と実態とは

多肉植物(サボテンやセダムなど)の農家も観葉植物農家に近い仕事で、年収は規模によって大きく変わります。
多肉植物はここ数年ブームになり、「タニラー(多肉植物愛好家)」という言葉が生まれるほど人気のジャンルです。小さな鉢で可愛らしく育てられるため都市部でも需要が高く、副業から本業にする人も出てきています。多肉植物農家の年収も観葉植物農家と同様にピンキリですが、おおまかな目安としては小規模では100万~200万円、中規模以上で効率的に経営できれば500万円以上も目指せると言われます。さらに、高付加価値のレア多肉を扱う大規模農家では1,000万円超の年収を得る例もあります。
多肉植物農家の特徴と収益構造ですが、 多肉植物は観葉植物と比べて育成コストが低めなのが利点です。乾燥に強く水やり回数が少なくて済むため、管理が比較的楽で人手や水道代の負担が小さいです。またサイズが小さく軽量なため、通販での発送コストも抑えやすいという経済的メリットもあります。特に希少種や改良品種の多肉植物はコレクター人気が高く、一株数万円で取引されることも珍しくありません。こうした高単価品を扱えれば収益性はぐっと高まるでしょう。一方で、多肉植物市場も競争が激しく流行の移り変わりがあります。ブームに乗り遅れて大量の在庫を抱えるリスクや、育てやすいとはいえ病害虫が発生すると一気に品質が落ちて売り物にならなくなるリスクも存在します。また近年は人気が高まるあまり、希少な多肉の盗掘や違法取引が問題化しており、農家も種苗法などの法令をしっかり遵守して運営することが求められます。
かつてサボテン収集が趣味だったGさんは、副業で増やした多肉植物をネット販売していたところ注文が殺到し、本格的に多肉植物農家に転身しました。彼はネットオークションで独自に交配したハオルチア(一種の多肉植物)を売り、一株数万円の値が付くこともあったそうです。その結果、副業時代は年収50万円ほどだったのが、専業にしてから500万円超と大幅アップしました。今では温室を増設し、海外にも販路を広げています。
一方、失敗例としてはHさんのケース。多肉ブームに乗って起業しましたが、市場調査不足でニッチすぎる種類ばかり揃えてしまい、一般客に全然売れませんでした。在庫を抱え赤字続きで、「売りたいものではなく売れるものを育てるべきだった」と反省しています。また、Hさんは希少種の輸入販売にも手を出しましたが、輸入手続きの煩雑さや植物検疫の知識不足からトラブルになり、経営を圧迫しました。このように、多肉植物農家もマーケット感覚とビジネススキルが欠かせないことが分かります。
多肉植物農家は観葉植物農家と同様、情熱と戦略があれば収入を伸ばせる仕事です。
「好きこそものの上手なれ」で、多肉植物愛好家が高じて成功するパターンはよくあります。ただし、趣味感覚のままでは利益を出すのは難しく、やはり経営マインドが必要です。幸い多肉植物は繁殖が比較的容易で、挿し木や株分けですぐ増やせるため、元手が少なくても始めやすいメリットもあります。小さく始めて人気品種をコツコツ増やし、ファンを増やしていけば、それがしっかり年収につながっていくでしょう。観葉植物農家志望の方で多肉好きなら、まずは副業タニク農家から挑戦し、ノウハウをつかんでみるのも一案ですね。
【観葉植物と似ている仕事その②】花卉農家の年収と実態とは

花卉(かき)農家とは切り花や鉢花など観賞用の花を育てる農家で、観葉植物農家と重なる部分も多いですが市場規模は大きく平均年収は約300~400万円程度です。
農林水産省のデータによれば、全国の花卉農家の平均年収は約314万円と報告されていますagrijob.jp。しかしこの数字には経営規模の大小が反映されており、実際には大規模経営で年収1,000万円超から、小規模で100万円台まで様々です。花卉農家はバラやカーネーションなどの切り花を専門にするケースと、シクラメンやランなど鉢物を育てるケースがあり、観葉植物農家より伝統がある分野です。
花卉は冠婚葬祭や贈答需要が根強く、狭い面積でも高収益が期待できると言われます。例えばバラや洋ランなどは1本あたりの単価が高く設定でき、温室で計画的に咲かせれば少ない面積でも十分な収入を上げることが可能です。実際、都市近郊の小さな温室で高品質なバラを周年生産し、年収数千万円規模の売上を上げている農家も存在します。また花はイベント需要が大きく、母の日や卒業式シーズンなど年中行事に合わせ売上ピークを作れるのも強みです。「一番儲かる花は何か?」という問いには難しい側面もありますが、やはり人気と需要が安定して高いバラや胡蝶ランはトップクラスでしょう。特に胡蝶ランは企業の開店祝いなどで大量注文が入り、高単価で取引されます。一方で花卉農家にも課題はあります。設備投資と維持費がかかるのは観葉植物同様で、温室の光熱費や苗の導入コストが利益を圧迫します。また、花の場合は咲く時期をコントロールする技術が重要で、出荷のタイミングを誤ると需要期を逃し値崩れすることもあります。さらに輸入切り花との競合もあり、価格競争も厳しい世界です。それでも、直販や新品種の開発などで付加価値を付ければしっかり稼げる分野でもあります。
花卉農家の実態例ですが、 老舗の花卉農家Iさん(50代)は、親の代からのバラ農家です。温室面積は30aほどと決して大規模ではありませんが、高級ホテルやブライダル向けに品質重視のバラを出荷し、年間の売上は数千万円に及びます。Iさんの年収(所得)も推定で700~800万円と、一般的なサラリーマンを上回ります。成功の秘訣を尋ねると、「うちは品質一本。市場に出さず固定客に直販してる」とのこと。実際、市場経由だと1本100円のバラが、ホテルに直接卸すことで1本200円以上になり、利益率が全然違うそうです。このように販売先の工夫で収益を倍増させるケースは花卉農家では珍しくありません。一方、新規就農で花卉に挑戦したJさん(30代)は、チューリップ栽培で苦戦しました。露地で栽培したところ天候不良で開花が揃わず、市場に出せる品質が確保できなかったのです。結局その年の所得は100万円程度と赤字ぎりぎり。翌年から施設(ビニールハウス)栽培に切り替えましたが、今度は設備投資の借金返済が重くのしかかり、なかなか利益が出せないといいます。このように、花卉農家はハイリスク・ハイリターンな面もあります。巧くいけば高収入が得られますが、軌道に乗るまでは設備投資や技術習得に時間とお金がかかることも肝に銘じておく必要があります。
花卉農家は観葉植物農家と同様に夢のある仕事ですが、計画性と技術力が収入を左右します。 平均年収は先述の通り300~400万円台ですが、これは古参の兼業農家なども含めた数字です。専業で先進的経営を行えば、その倍以上の収入も十分狙える分野です。特に観葉植物農家から花卉農家へ転身したり両方手掛けたりするケースもあります。観葉植物のノウハウは花卉にも活きる部分が多いですし、その逆も然りです。「花も葉も愛するグリーンのプロ」として幅広くチャレンジすれば、収入源も増やせるでしょう。観葉植物だけでなく花の栽培にも興味がある方は、両輪で経営することでリスク分散と収益最大化を図ることも可能です。美しい花を咲かせ、そして懐にも花を咲かせられるよう、技術と経営を磨いていきましょう。
【観葉植物と似ている仕事その③】ハーブ農家の年収と実態とは

ハーブ農家とはバジルやミントなど香草を専門に育てる農家で、観葉植物と同じく需要が高まっています。
年収は専業か副業かで大きく異なり、専業では100万円未満~数百万円、副業なら数十万円から始めて500万円以上稼ぐ人もいるようです。ハーブは需要が途切れにくく初心者にも育てやすい植物なので、農業未経験者が参入しやすい分野でもあります。
ハーブの魅力は何と言っても需要の幅広さと安定性です。料理の香味料として、ハーブティーやアロマオイルの原料として、また観賞用や虫除け用途まで、用途が多彩で常に一定のニーズがあります。特に昨今のナチュラル志向で、オーガニックハーブティーやハーブコスメなどの市場が拡大しており、ハーブ栽培ビジネスは儲かる副業としても注目されています。ハーブ農家の収入は、栽培する品目や販売方法によって変わります。例えば高級レストラン向けのフレッシュハーブを契約栽培すれば安定収入が見込めますし、観光農園としてハーブ摘み体験を提供すれば入園料などの収入もプラスできます。一方、ドライハーブや精油の加工まで手掛けると、設備投資や加工の手間がかかりますが、製品単価が上がるため利益率は向上します。副業として庭先でミントやローズマリーを育て、マルシェで少量販売する程度なら年に数十万円の収入でしょうが、本格的に畑で栽培しネットショップ等で販売すれば年収500万円を超えることも珍しくありません。中には1,000万円以上稼ぐハーブ農家も存在しますが、それはかなり成功した例であり、誰もがすぐに達成できるものではないでしょう。ハーブ栽培自体は比較的簡単とはいえ、収益化にはマーケティングとブランド作りが重要です。
ハーブ農家の事例ですが、 Kさんは地方移住して夫婦でハーブ農園を始めました。初期投資は畑の造成や苗購入など約100万円ほどで、家庭菜園の延長のような小さなスタートでした。しかしSNSで発信を続けた結果、地元カフェからハーブの注文が入るようになり、品目を増やしながら徐々に規模拡大。3年目には年間売上1,200万円、所得600万円に達したそうです。これは「日本一小さい農家が日本一濃密に稼ぐ」とメディアにも取り上げられたほどの成功例です。彼らはハーブ苗も生産販売し、ワークショップでファン作りも行うなど多角的に工夫しています。一方、都市近郊で副業ハーブ農家をしているLさんは、週末だけで育てられる範囲でハーブを栽培し、収穫物をハーブティーに加工してネット販売しています。趣味と実益を兼ねて楽しみながら続け、副収入は年間50万円程度とのことですが、将来的に引退後は本腰を入れてハーブ園をやりたいと夢を語っています。このようにハーブ農家はライフスタイルに合わせて柔軟に収入規模を調整できる点も魅力です。
ハーブ農家は小規模でも始めやすく、需要に応じて収入を伸ばせる可能性があります。 ハーブは強健な種類が多く、狭いスペースでも栽培可能なので、都市部のベランダや空き地でもビジネスにできます。特にミントやバジルなどは成長が早くどんどん増えるため、生産性が高いです。もちろん質の高いハーブを提供するには適切な品種選びや栽培方法の工夫が必要ですが、園芸初心者でも扱いやすい植物と言えます。観葉植物農家を目指す人にとっても、まずハーブ栽培で腕試ししてみるのは良いステップになるでしょう。例えばバジルをプランターで大量栽培して飲食店に卸してみるとか、ラベンダー畑を作って観光客を呼ぶとか、アイデア次第で色々な展開が可能です。収入面でも、一度軌道に乗れば観葉植物に劣らない収益を上げることも夢ではありません。「ハーブ=薬草」と呼ばれるように昔から人々の生活に根付いた植物ですから、その魅力を伝えビジネスにつなげるやりがいも大きいですよ。
【みんなが悩む疑問を解決します!】観葉植物の農家の年収や仕事内容に関するよくある質問5選
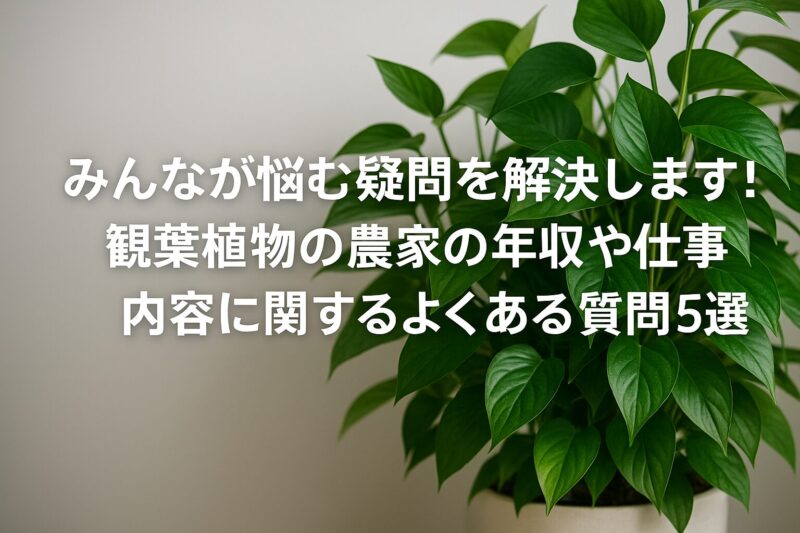
Q1: 観葉植物農家になるのに資格は必要?

A: 特別な公的資格は必要ありません。農業一般に免許や試験はないので、誰でも始めること自体は可能です。ただし、観葉植物の栽培には専門知識が不可欠なので、実際には農業大学校や研修で学んだり、園芸店で経験を積む人が多いです。また、事業として始める場合は農地法の許可や設備投資が必要になるため、計画と準備が重要です。資格はなくても「知識と経験」という無形の資格を身につけておくことが成功の鍵ですね。
Q2: 観葉植物農家を始めるには初期費用はいくらぐらい必要?

A: 規模によります。自宅の庭や小さなビニールハウスで始めるなら数十万円程度から可能です。例えば中古のビニールハウス設置や苗の仕入れで50~100万円程度でスタートした例もあります。一方、広い農地を取得し大規模温室を建てるとなると数千万円規模の投資になるでしょう。農林水産省の資料では新規に農業を始める際、一般的に3,000~4,000万円の初期資金が必要との指摘もあります。観葉植物の場合、温室や育成設備(暖房・照明など)の費用が大きいです。ただし補助金や融資制度も充実しているので、自己資金ゼロからでも計画次第で開業可能です。まずは小規模に始め、徐々に設備投資するのが現実的でしょう。
Q3: 観葉植物農家は副業や兼業でもできますか?

A: できます。実際、副業で観葉植物を育てて販売し、ゆくゆく独立を目指す人もいます。平日は会社勤めをしながら、週末に自宅温室で植物を育てネット販売するといった形です。ただし生き物相手なので、平日でも水やりなど最低限の世話は必要です。その点、多肉植物やサボテンなど手間の少ない種類から始めるのは副業向きです。副業で年に数十万円稼げれば上出来ですが、軌道に乗れば副業でも年収500万円以上稼ぐ人もいます。兼業の場合、本業の農家が野菜と観葉植物両方を育てて収入源を増やすケースもあります。時間管理は大変ですが、逆に本業の安定収入があることで観葉植物栽培に挑戦しやすいメリットもあります。まずは副業で初めて、需要や栽培に自信がついたら本業に移行するステップを踏むのも良いでしょう。
Q4: 観葉植物農家はどうやって植物を販売するの?販路は?

A: 大きく分けて卸売と直販があります。卸売は花き市場や問屋に出荷し、園芸店などに並ぶ形です。メリットは大量に売れることですが、価格は市場相場に左右されます。直販には直売所・ネット販売・契約販売など様々です。直売所では自分の農園や道の駅などで直接お客様に販売します。ネット販売は自社ECサイトやフリマアプリ、SNS経由で全国に販売できます。契約販売は企業や店舗と直接取引する形で、例えばインテリアショップに定期的に観葉植物を納品したり、オフィスグリーンのレンタル契約を結んだりです。最近はサブスクリプション(定期便)も新しい販路で、月額料金で季節の観葉植物を届けるサービスも登場しています。観葉植物農家のFさんは、Instagramでファンを増やしDMで注文を受けるSNS直販で成功していますし、別のGさんは地元のカフェと契約して店内装飾用の植物をレンタルし安定収入を得ています。このように販路次第で売上も年収も大きく変わるので、自分に合った方法を組み合わせることが大切です。
Q5: 観葉植物農家にとって「儲かる観葉植物」って何?どの品種が狙い目?

A: 一概には言えませんが、需要が高く高単価で売れる種類がやはり儲かります。具体的には、インテリア人気のあるモンステラやフィカス・ベンガレンシス(ゴムの木)など大型観葉や、珍しい斑入り(はんいり)品種は高値で取引される傾向があります。最近では斑入りモンステラがコレクター間で高額取引され話題になりました。またオーガスタやユッカなど耐陰性があってオフィスや店舗装飾に人気の植物も安定して売れます。小型ではテラリウム用の観葉植物(フィットニアやピレアなど)も密かなブームで、セット販売すると利益率が高いです。とはいえ、流行は変わるので「これさえ育てれば一生安泰」という品種は無いのが実情です。重要なのは市場のニーズを常にリサーチし、売れ筋をタイムリーに育てること。実績として、一番儲かる花卉品目はバラやランですが、観葉植物ではトレンドを捉えた希少種が一時的に大儲けになることがあります。例えば数年前にブームになった「アグラオネマ・ピクタム トリカラー」という珍奇植物は、一株数万円にもなりました。しかしブームが去ると価格が落ち着くので、儲かったうちに次の手を打つ必要があります。結局、「儲かる植物=自分が強みを持てる植物」とも言えます。他人が儲かっている品種を真似するより、自分が情熱を注げる植物で品質や量を極め、それを必要とするお客様に届けるのが一番の近道でしょう。
読者が今日から始められる!観葉植物農家を目指す第一歩とは?

観葉植物農家への道は長く感じるかもしれませんが、第一歩は意外と身近なところから踏み出せます。ここでは、今からできる具体的なアクションをご紹介します。
- ステップ1:知識を深めるための本を読む。
プロのノウハウが詰まった本で勉強を始めましょう。例えば、観葉植物栽培の第一人者・杉山拓巳さんによる『NHK趣味の園芸 観葉植物パーフェクトブック』(NHK出版)などは約200種類の育て方や管理法が網羅された必携の一冊です。基本から応用までカラー写真付きで解説されており、初心者でも楽しく学べます。まずは一読して観葉植物マスターへの知識を蓄えてください。
- ステップ2:小さくてもいいので植物を育ててみる。
机の片隅やベランダでも構いません。実践に勝る教師なし!手始めに育てやすい観葉植物を数鉢育ててみましょう。最近は初心者向けに必要なものが揃った「観葉植物栽培セット」も売られています。例えば下記の【東京寿園 観葉植物5種セット (ハイドロカルチャー)】などは、土を使わずに室内で育てられる小さな観葉植物が5鉢セットになっており、水耕栽培用の容器と栄養剤も付属して初心者にピッタリです。こうしたキットを使えば手軽に複数の植物を同時に育てられます。毎日の水やり・観察を通して、生長の喜びや難しさを体感しましょう。失敗して枯らしてしまっても大丈夫! むしろ失敗から学べることは多いです。私も初めて買ったゴムの木を水のやり過ぎで枯らしてしまったことがありますが、「過保護はいけない」と身をもって学びました…。小さな成功と失敗の積み重ねが、将来の大きな成功に繋がります。
- ステップ3:生産者や先輩に会いに行く。
可能であれば近所の園芸農家や植物店を訪ね、話を聞いてみることをおすすめします。直売所がある観葉植物農家なら直接訪問して「将来こういう仕事に興味があるんです」と聞けば、きっといろいろ教えてくれるでしょう。現場を見ることでモチベーションも上がりますし、人脈づくりにもなります。最近は観葉植物農家が主催するワークショップや体験イベントも増えています。そういった催しに参加してみるのも貴重な体験です。筆者も先日ハーブ農家の見学会に行きましたが、土の香りや温室の熱気を肌で感じ、「これを仕事にするのも素敵だな」と胸が高鳴りました。 - ステップ4:計画を立てる。
最後に、将来的に観葉植物農家になるためのざっくりとしたプランを書き出してみましょう。いつまでに何をするのか、例えば「○年後にビニールハウスを建設」「まずは副業で月商○万円達成」など目標を設定します。プランは変更しても構いません。紙に書くことで夢が具体性を帯び、行動に移しやすくなります。「夢を語るだけで終わらせない」のがポイントです。計画がある人とない人では、5年後10年後に大きな差がつきます。
さあ、できることから始めてみましょう! 観葉植物農家への道は一本ではありません。知識を蓄える、本格的に育ててみる、人に会う、計画する――どれも今日からできる第一歩です。小さな一歩でも踏み出せば景色は変わります。緑の仲間たち(植物)とともに、あなたの夢の苗を育て始めてください。
まとめ

観葉植物農家の年収は、一概に「○○万円」と断言できない幅がありましたが、その背景には経営努力次第で収入をコントロールできる可能性が秘められていることがお分かりいただけたと思います。平均は300~500万円程度とされつつも、市場ニーズの掴み方、販路の開拓、コスト管理によって年収1,000万円超も狙える世界であり、一方で準備不足だと100万円台に甘んじてしまう厳しさもあります。【観葉植物 農家 年収】というキーワードの答えは、「あなた次第で大きく変わる」というのが正直なところでしょう。
観葉植物農家の現状と課題から始まり、始め方のステップ、年収の実態やアップさせるポイント、そして将来性まで幅広く見てきました。需要拡大や技術革新でこの業界の未来は明るく、「緑のある暮らし」を支える観葉植物農家という仕事には大きな社会的意義もあります。似た職業である多肉植物農家や花卉農家、ハーブ農家の情報も比較することで、自分が進みたい道筋がより明確になったのではないでしょうか。いずれも植物を愛し、その価値を届ける素敵な仕事です。
最後に、この記事で解決したQ&Aも振り返ってみてください。資格は不要、初期費用は小さく始めてOK、副業からでも挑戦可能、販路次第で収入増、そして儲かるポイントは需要に応じた戦略と独自性でした。大切なのは情熱と継続、そして学ぶ姿勢です。小さな苗もコツコツ育てればやがて大樹になります。あなたの観葉植物農家への夢も、ぜひ今日から水やりを始めて育てていってください。この記事がその第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。応援しています!
🌿おまけトーク ~ホームセンターで“立ち止まる理由”ができました~

ある休日の午後、ふとテレビをつけたら、“観葉植物を育てる若き農家”の再放送中。
ちょっとだけ見るつもりが、気づけばお茶も冷めていて、目はウルウル、心はジーン。
番組に登場していたのは、山あいの田舎で観葉植物を育てている青年。毎朝4時に温室へ行き、葉の一枚一枚を手で拭きながら「今日も綺麗に育ってくれてありがとう」とつぶやいていたのが印象的で…。
その姿はまさに、“グリーンの育て親”。
そして出荷のシーンで、梱包前の植物に向かって「うちの子たち、頼むから新しいおうちで可愛がってもらえよ~!」と笑いながら見送るその背中。
まるで我が子を送り出す親のようで、思わずこちらも「大切にするからね!」とテレビ画面に向かって返事をしてしまいました(笑)。
それ以来、ホームセンターの園芸コーナーに並ぶ観葉植物を見る目が変わりました。
「この子も、あんな感じの温室で育ったのかな…」なんて妄想が止まらず、気づけばモンステラを1鉢お迎え。お迎え後はもう、水やりタイマーを導入し、葉拭き用クロスも新調して、気合いの入れ方が違います(過保護気味?)。最近は“土の乾き具合チェッカー”まで検討中です。
ちなみにですが、モンステラの名前、実は“しずく”ちゃんにしました🌱
理由は、朝の葉水をあげると、葉先からポトン…と小さな雫が落ちるから。今では毎朝、「今日もキラキラ育ってね」と声をかけるのが日課です🌞
植物を通じて、誰かの想いが暮らしの中にそっと入り込んでくるって、なんだか不思議で、あたたかいですね。これからも、“しずく”と一緒に、小さな命を大切に育てていきたいと思います。
参考文献:
- Nursery Management (Garden Center magazine) “A maturing market – 2023 Houseplant Report”nurserymag.comnurserymag.com.
- CNBC Make It “44-year-old’s garage side hustle brings in $148,600 a year selling houseplants online” (2024)facebook.com.
- University of Georgia Extension “Growing Indoor Plants with Success”extension.uga.edu.
- Plant Cell Technology Blog “Is Tissue Culture a Profitable Technology for Plant Businesses?


